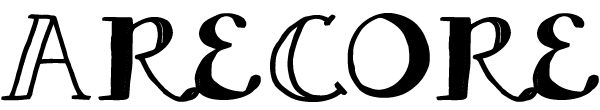だいたいの小学校では、3年生から国語辞典を使用した授業が始まりますね。
我が家の子どもが通う小学校も、辞典の使用は3年生の1学期からでした。
私が小学生の頃は学校から支給されて、みんな同じものを使っていた記憶なんですが、今は違うんですね~。
各々、自分の辞典を持ってくるスタイル。
息子から聞いたところによると、学校の授業では、
「ぼくの辞典にはこう書いてあるよ」
「私のはこうだった!」
というようなやりとりもされているとのこと。
いろんな解釈や言い回しを知ることができて良い授業だなと思いました。速引き競争なんかもしているそうです。
自宅学習ではいつから使う?
我が家では小学1年生の2学期頃から、自宅で国語辞典を使っていました。
「これ、どういう意味?」と聞かれてうまく説明できないことが増えたからです。
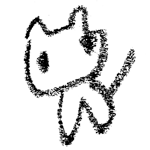
1年生でも『あかさたな』の並び方を覚えてさえいれば、ちょっと説明すればすぐに引けるようになります。
私が「あれどういう意味だっけ?辞書で引いて教えてよー!」というと喜んでやってくれる時期でもありました。
(3年生になった今では多少めんどくさがります。笑)
テレビを見たり本を読んだりしていて、わからない言葉、わからない漢字が出たら辞書を引く、という習慣づけを1年生から徐々にしていきました。
とはいえ、「辞書で調べてみたら?」という声かけはかなり必要かと思います。
小学生用と一般用を併用する
3年生くらいになり、読む本もちょっと複雑なものになってくると、小学生用の辞典では載っていない単語もちらほら出てきます。
我が家では、その頃から一般用(大人用)の辞典も併用するようになりました。
辞典は学校にも持っていかなければいけないので、小学生用をさらにもう一冊買い足しています。
一般用の辞典は、字がかなり小さくなり、言い回しもちょっと難しくなりますが、引き方は同じなので小3なら十分に使うことができます。
ただ、慣用句などは小学生用にしか載っていないものもありましたので、高学年になっても、小学生用も手元に置いておいたほうが良いかなと思います。
一般向けはコレを使っています
小学生用はこちら
※こちらは現在は第7版が販売されているようです(2020.1現在)
どちらも引いてみて違いを見つける
小学生用の辞典にも載っているけど、こっちではどう書いてあるかな?と見比べてみるのも楽しいです。
我が家が使っているのは、どちらも三省堂のものですが、例えば「みぎ(右)」と調べると
小学生用:「北をむいたときに東にあたるほう」
一般向け:「アナログ時計の文字盤に向かった時に1時から5時の表示のある側」
と出てきます。
なるほどぉ!こんな説明があるのかー!
と思うと同時に、これ、小学生用と一般用、逆の方が伝わりやすくないですかね?!と思ったり。笑
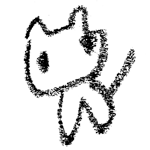
と、こんな発見があるのも楽しいです。
辞典は必ず箱から出しておく
辞典は、買ったらすぐに箱から出して本棚に並べておきます。
箱に入っていると、調べるまでに一手間かかるので、辞典に手が伸びにくくなるからです。
余談ですが、図鑑のカバーも見る時に邪魔なので外しています。
古すぎる辞典は買い換えがおすすめ
私も昔はなかなか古い辞典の捨てどきがわからず、小学校のときもらったものや、高校生の頃使っていたものが長いこと自宅にありました。
新しい語句もかなり増えているはずですので、まだ昔のものを使っている、子どもにも使わせている、という場合は、なるべく早めに買い替えるのが良いかな?と思います。
国語辞典に乗っていない言葉はネットで
どちらの辞典を調べても載っていない言葉(例えば何かの専門用語や、最近登場した言葉など)が出てきた場合は、息子が自分自身でネット検索で調べています。
2年生のある時、「ローマ字がわかればパソコンが使える!」という知識を入手したらしく、大人に聞き聞き、自分でローマ字表を作り、最初はそれを見ながらキーボードを叩いていました。
今では表は見ずに打つことができるようになったので、次はブラインドタッチを目指してタイピングゲームなどで遊んでもらっています。
パソコンは、基本的にいつでも使って良いということにしてありますが(だいたい、言葉の意味、ゲームのことを調べています)ゲームやおもちゃのことを調べている時は、見せたくない広告などが現れることがありますので、必ず目が届くようにしています。
我が家の国語辞典事情はこんな感じです。
普段から、大人が使うような言葉もそのまま会話に取り入れて、「それってどういう意味?」という言葉を引き出すことを心がけています。
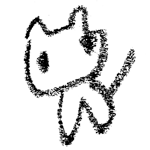
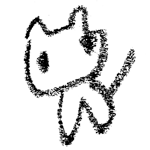
なにかご参考になれば嬉しいです。
ここまでお付き合い頂きありがとうございました。